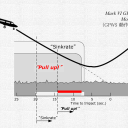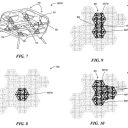旅客機は地球上で一番安全な乗り物というのは本当?
「今日も空港は快調に営業中です。飛行機はみんな元気に飛んでいます」
テレビのニュースで、インターネットの報道でも、そう報じることはまずありません。
通常は、天気予報のついでに「今日は飛行機の欠航はありません」と報じるくらい。油断すると聞き逃しそうな短い報道です。
ひとたび飛行機事故が起きると、大勢の記者や報道カメラマンが急いで会社から出発し、空港や事故現場に駆けつけて大きく報じます。
その結果、飛行機事故の報道ばかりが目だってしまい、「車のトラブルや事故が報道されない日はないが、飛行機トラブルは報道されない日の方が多い」とは、なかなか気づきません。
それに確率的に、日本の人口では500人規模の事故や事件が起きると、知人の知人くらいの人に、一人くらいは事故の関係者がいると言われています。飛行機といえば事故のイメージが強いのは、仕方ない部分があるのです。
日本で初めて車の事故が起きたのは、明治時代のこととされています。それまでは日本に自動車がなかったからです。江戸時代という説もあります。大八車と人が衝突事故を起こすのは、運転者側の過失だとして、法律や刑罰が設けられていたからです。
日本で最初に人が空を飛んだのは、江戸時代。9世紀説もありますが、いずれも動力なしの飛行で、事故の話はありません。日本初の動力つき飛行機の事故は、大正時代の出来事とされています。
飛行機は車より歴史が短いのに、車より事故の確率が少なく、「世界一安全な乗り物」という評価まで得ている。これには理由があります。
たとえばあなたが「車で旅行に出かけよう」と考えたとします。何年も実車と現場で訓練を積んだ、優秀な運転手つきの車です。
運転手はいきなり車に乗りこんで、あなたを客席に乗せて、エンジンをかけたりはしません。
まず、専門知識を持つトラベルプランナーに依頼し、目的地まで安全に旅行できるルートを設計してもらいます。天候はどうか、道路が混む心配はないか。途中でお腹がすいたとき、買い物したくなったとき、目的地を変更したくなったとき。
あらゆる可能性を検討した計画書を作って、運転手がチェックし「OKです。このルートで行きます」とサインします。
同時に、整備士さんに車を点検・整備してもらいます。
この点検は車が出発する時、帰ってきた時、毎回必ず行っています。旅行当日だけでなく、常に定期点検を行っていて、大切に手入れされている車です。数年に一度は、部品一つずつになるまで解体して点検。きれいに部品掃除をしてから組み立てます。
車体の塗装もいったんはがして、新しく塗りなおしますから、新品同様です。
いよいよ出発となったら、運転手は車に異常がないか、発車するときジャマなものが置いてないか、周囲を見回ってから運転席に座ります。
運転席に座ったら、また点検です。
ハンドル、ブレーキ、アクセル、他の装置もすべてチェックし、点検記録もつけます。
ようやくあなたに、乗ってください、出発ですと声をかけます。あなたの荷物も車に積み込みます。
出発するのはその後ですが、人間の運転が間違っていては台無しですから、すっかり憶えているマニュアルでも、毎回きちんと読み直します。
目的地についたら、あなたが観光を楽しんでいる間、車の点検をします。目的地に別の整備士さんが待っていて、点検・整備をしてくれるのです。
あなたが観光を終えて、運転手に「もう家に帰りたい」と言った頃には、整備士さんは仕事を終えて、車の準備ができています。運転手は帰り道でも、出発のときと同じチェックをしてから運転します。
すべての旅客機は、フライト一回ごとに、この車と同じような作業を行っているのです。
きわめて充実した点検・整備ですが、それでもチェックできないポイントがあります。
「旅客機で使われている電波」と「乗客が機内で発信した電波」が混在したとき、飛行に支障ないかどうかを検証することです。どちらの電波も、数と種類が多すぎて、「混在したとき何か起きるか、何も起きないか」を検証しきれません。
飛行機で使われている電波が多いのは、飛行機が把握すべき情報が非常に多いからです。
地上から一気に高度1万メートルまで上昇、時速約1,000kmで超長距離を移動する物体の周辺環境は、刻々と変化します。
そうでなくとも上空の気象条件は厳しく、たえまなく変化しているのです。
気象の変化に対応し、合理的なルートを選び、同じ速度で飛んでいる他の飛行機とぶつかることなく、無事に目的地に到着する。そのためには大量の情報を収集し、迅速に分析し、時速1,000kmのフライトに反映しなければなりません。
情報を集めたり、フライト中必要な通信を行うために、飛行機にはたくさんのアンテナがついています。
たとえばジャンボ機なら、機体前方だけでグライド・スロープ&ローカライザ受信、ATCトランスポンダー、DME、マーカー・ビーコン、ADF、HF、VORなどのアンテナがあります。。
このアンテナで通信や情報交換を行う相手は、ローカル・コントロール、クリアランス・デリバリー、ディパーチャーなど。パイロットと管制官など、人間同士で行う通信がほとんどです。
人間と機械、機械と機械同士で行う情報交換もあります。
ATIS、ACARS、CVR、FIR、FMS、GPWS、ILS、VORTAC、PFD、TCASなどです。
それぞれで使われる電波の種類・周波数などが違いますから、一度のフライトで飛行機が使う電波の数は膨大なものです。ここに乗客の持ち込んだ電子機器の電波が混在したとき、なにか起きるか起きないかは予測しきれません。
小さな電子機器を起動しただけで、全長数十メートルの巨体を持つ旅客機に影響するはずがない。電波の性質はそういうものではありませんが、乗客の大半はそのことを知りません。
それに、長年の統計で、航空機事故の80パーセントが「離陸からの3分間」「着陸までの8分間」に起きることがわかっています。
旅客機が重視するのは快適性ですが、そこに安全が伴っていなければ意味がありません。
離着陸時、乗客に電子機器の使用を許可してよいかどうか。航空業界が常に慎重なのは、お客さまの安全を第一に考えているからです。